室町?戦国時代につくられた国字は表意性が豊かで非常に面白いが江戸時代ではすっかり消えたものがほとんど。14?16世紀当時の国語辞書や漢字字書に新しく載り始めた国字で思いつくものを書くとこんな感じ。 pic.twitter.com/aRecCXtv0y
-- 拾萬字鏡(漢字情報総合) (@JUMANJIKYO) 2018年6月8日
鎌倉時代の国字も見たいとあったので鎌倉時代の辞書に載ったインパクトのあるのと分かりやすい国字だけ紹介... pic.twitter.com/rFS6Lrgotb
-- 拾萬字鏡(漢字情報総合) (@JUMANJIKYO) 2018年6月8日
平安時代(12世紀頃まで)に現れる国字。日本人が国字をうみだしたのは7世紀頃からで現在も使用されている国字「畠」「樫」は創製期に近い。この時代の国字も表意性はあるといえ古い日本語も多く現代では分かりにくいものも多い。 pic.twitter.com/JO8AUjDNCd
-- 拾萬字鏡(漢字情報総合) (@JUMANJIKYO) 2018年6月8日
江戸時代の国字。江戸時代の場合、辞書に正式に載った国字は「俤」「噺」「?」「?」など数十文字で少なく民間で用いられる国字が多かった。奇数題名が好まれ特に本や歌舞伎の題名に国字を使うことが流行した。 pic.twitter.com/Cxosb5F4JH
-- 拾萬字鏡(漢字情報総合) (@JUMANJIKYO) 2018年6月8日
国字に「花」がつく字は多いです。「花が咲き散る姿こそうつくしい」という無常観、もののあはれを見出す日本人独特の感性なんでしょうね。 pic.twitter.com/XhbRNtqtXW
-- 拾萬字鏡(漢字情報総合) (@JUMANJIKYO) 2018年6月9日


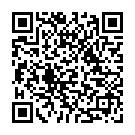
コメントする